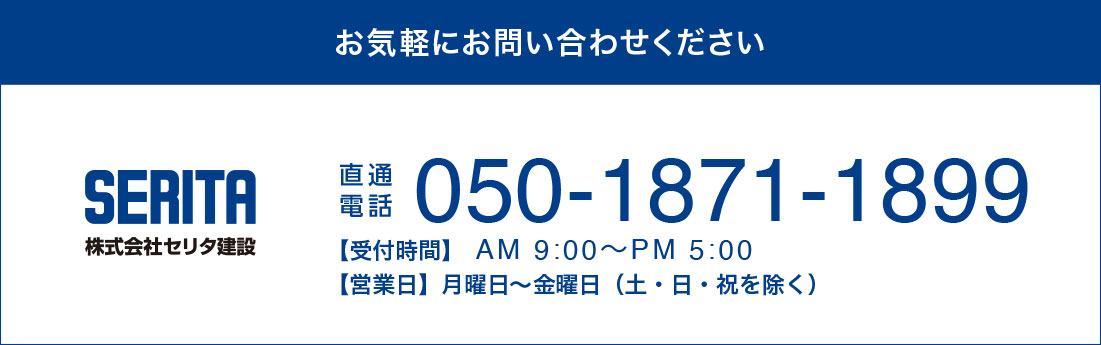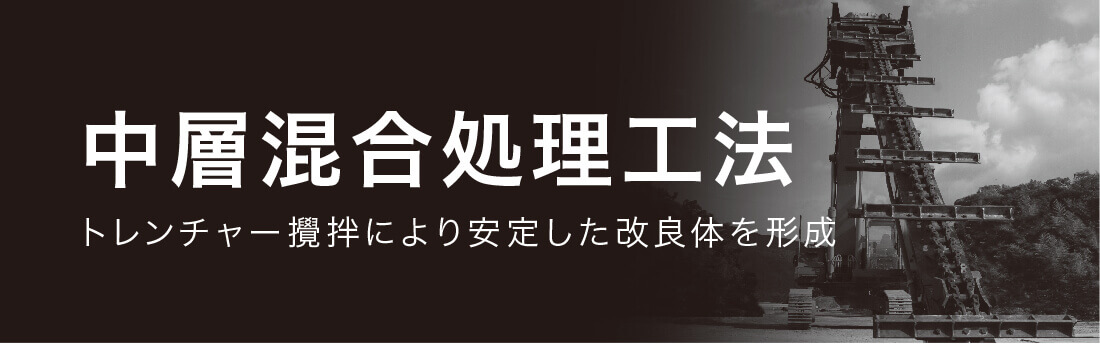地盤改良・コスト削減を同時に実現!費用を抑える具体的方法
2025年04月25日 地盤改良
建設工事で安全かつ経済的な基盤を作るうえで地盤改良のコスト削減は欠かせないテーマです。地盤調査から施工計画、発注方式までを最適化すれば、大幅なコストダウンを実現できる可能性があります。
本記事では、具体的な地盤改良工法の選定方法や費用削減のポイントについて解説し、現場の設計・コンサル・発注担当者が知っておくべきノウハウをまとめます。

地盤改良におけるコスト削減を左右する要因と現在直面している課題
地盤改良をする際、コスト削減の鍵となるのは地盤の性質を正確に把握し、適切な施工方法を選択することです。
しかし、実際の工事現場では地盤調査が不十分だったり、施工プロセスが複雑化したりすることにより、予想以上の費用が必要になるケースも少なくありません。ここでは、地盤改良でコストを圧迫しがちな要因と、その背景にある課題を整理します。
高額な施工費の要因を理解する
地盤改良の施工費が高騰する原因として、まず挙げられるのが「工法選定のミスマッチ」です。
地盤の強度や水分量・土質の分類を正確に把握していないまま施工を始めると、必要以上に大がかりな機械を用いたり、過剰なセメント改良材を投入したりするなど、コストがかさむ要因につながります。
加えて、工期の延長も大きな出費を伴う要素の一つです。地盤改良の工期が延びれば延びるほど、人件費や機械の稼働費、材料の保管費などが積み重なります。とくに大規模な工事ほど、地盤の不均一さや天候の影響を受けやすく、思わぬ工期の長期化の恐れがあります。
これは発注者側が十分な余裕を見越していなかったり、施工計画が甘かったりする場合に起こりやすい問題です。
さらに、地盤改良後の品質に対する不安から、再度の補修や追加工事が発生することもあります。これは、初期の地盤調査が正確でなかったり、設計段階での想定が甘かったりしたことが原因であり、結果的に追加の費用を発生させてしまいます。こうした要因が複雑にからみ合うことで、コスト削減が思うように進まず、現場での負担が増えてしまうのです。
地盤調査の精度がプロジェクトを左右
地盤改良においてコスト削減を実現するためには、地盤調査の質がプロジェクトの成否を大きく左右します。
調査の精度が低いと、改良範囲の誤差が生じたり、想定していた地盤の強度と実際の数値が大きく食い違ったりする可能性が高まります。これにより、施工に入った段階で想定外のトラブルが発生し、工事を停止して再設計を余儀なくされるケースもあるのです。
地盤調査は、試掘やボーリング試験、各種土質試験など複数の方法を組み合わせることが重要です。調査結果が偏っていると、的確な工法選定が難しくなります。とくに不連続層や硬軟が混在する地盤では、部分的に異なる工法を使い分ける必要があるため、より入念な調査計画が求められます。
発注者や設計者の立場からすると、調査費用を最初に抑えたいと考えがちですが、ここでのコストダウンがのちの施工費増大につながるリスクを考慮しなければなりません。
調査に投資することで、最適な地盤改良工法を導き出し、トータルでの大幅なコスト削減を実現できる可能性があります。
地盤改良 コスト削減に効果的な工法と設計で費用を最適化するポイント
地盤の性質に合った最適な工法を選択し、かつ設計段階で必要な強度を的確に見定めることが、地盤改良 コスト削減の鍵です。過剰な安全率を設定したり、必要以上に広範囲を改良したりすると、結果的に施工費が上がってしまいます。
一方で、耐久性を確保しつつも適正な改良範囲・改良深度を設計することで、工期と費用の両面で効率化が図れます。
最適な地盤改良工法を選ぶための基準
地盤改良工法の選定には、大きく分けて以下の基準があります。
1.土質・地下水位
粘性土か砂質土か、地下水の存在状況はどうかなど、土質や地下水位の特徴によって適する工法が変わります。たとえば、セメント系固化材を使う工法は砂質土や粘性土のどちらでも適用可能ですが、地下水が多い場合には改良材が十分に効果を発揮しないこともあります。
2.必要強度・目的
建物の用途や荷重条件によって、求められる地耐力は異なります。道路や公共工事であれば長期間の耐久性が要求されます。簡易的な仮設工事であれば短期的な強度確保が主目的になるでしょう。必要強度を見誤ると、不要な改良範囲が広がり、コストを増大させる恐れがあります。
3.施工条件・工期
工事の期限や稼働できる重機の種類、施工可能なスペースなども工法選択の重要な要素です。狭小地での施工では大型機械の導入が難しく、改良方法を限定される場合があります。一方で、広いスペースが確保できる場合は大量の土を改良する大規模工法が選びやすくなります。
4.経済性と環境への配慮
施工時に発生する廃土の処理や騒音・振動など、環境への影響も見逃せません。社会的要請が強まるなかで、環境負荷を低減する工法の需要は高まっています。たとえば、浅層混合処理工法などは改良土の発生を抑えやすく、コスト削減と環境保全を両立させやすい手段となります。
これらの基準を総合的に検討し、最適な地盤改良工法を選択することが、コスト削減への第一歩です。
コスト削減と耐久性を両立させる設計
最適な工法を選ぶだけでなく、設計段階で「どれだけの地盤補強が本当に必要か」を正確に見極めることが重要です。過剰設計を避け、求められる地耐力と使用材料のバランスをとったうえで、施工領域を絞り込みます。
たとえば、建物全体を均一に改良する必要があるのか、柱状改良で要所を補強するだけで十分なのかなど、具体的な検討をすることでコスト削減の可能性が広がります。さらに、建物の基礎形状を工夫し、軟弱地盤を避ける形で配置変更するという手法も有効です。
設計段階で気をつけたいのは、安全率の設定です。安全係数を過度に高く設定すると、施工規模が余計に大きくなります。耐震性の向上や長期的なメンテナンス性を考慮しつつ、最適な安全率で設計を進めることが、地盤改良のコスト削減と品質確保の両立に直結します。
現場管理と発注手順で実現する地盤改良 コスト削減の具体的な手がかり
地盤改良の計画が適切でも、実際の現場管理や発注方式が不十分だと、当初の見積もりより大幅にコストが上振れする可能性もあります。工事全体を通して無駄を省き、円滑に作業を進めるためには、管理体制と発注手順の見直しが欠かせません。ここでは、現場レベルでのコスト削減につながるポイントを解説します。
工程管理で発生しがちな無駄を省く
現場管理における無駄の代表例として、資材や機材の手配の遅れ、作業スケジュールの不備、人員配置の不均衡などが挙げられます。とくに地盤改良は専門的な機材を使用することが多いため、タイミングを誤ると機材の待機時間や作業員の待機時間が増え、結果的にコストが膨れ上がる要因になります。
工程管理を徹底するためには、作業の前工程・後工程との連携を密にし、常に最新の進捗状況を関係者全員で共有することが重要です。小さな工事でも工程の「見える化」を図り、担当者間で連絡をこまめに取り合うことで、余分な待ち時間や資材の重複注文を防止できます。また、天候や地盤の状況が急変するリスクにも、予備案を用意しておくことが望まれます。
さらに、ICT(情報通信技術)の活用も有効です。地盤の3次元モデルを作成したり、施工管理ソフトでスケジュールを一元管理したりすることで、担当者間の情報共有が円滑になります。こうした取り組みにより、全体の工期短縮とコストダウンを同時に実現することが可能です。
発注方式の工夫でコストダウンを狙う
工事発注の段階で、設計・コンサル・施工業者が連携しやすい仕組みを作ることも、地盤改良 コスト削減に直結します。従来型の分離発注方式では、設計と施工が別々の契約です。そのため、後から「設計と現場が合わない」「積算が不十分で、追加費用が発生した」などの問題が生じやすくなります。
これを解消するために注目されているのが、ECI方式(Early Contractor Involvement)やデザインビルド方式(設計・施工一括発注)などです。設計段階から施工業者が参加することで、より実践的なコスト算出や工期短縮のアイデアを取り入れやすくなります。結果として、不要な地盤改良を避けたり、材料選定をスムーズにしたりできるので、総合的な費用削減が期待できるのです。
また、工事内容が明確であれば、総価契約方式を用いて施工の全体コストを固定する手法も考えられます。事前の調査と設計がしっかりと行われている場合には、追加費用が発生しにくいため、施工者にとっても発注者にとってもリスクを低減しやすいメリットがあります。
地盤改良とコスト削減を同時に達成するために押さえておきたい重要な視点
地盤改良で適切なコスト削減を実現するには、単に施工費を切り詰めるだけでなく、設計・調査・発注・工程管理の各段階を総合的に最適化することが重要です。まずは地盤調査に十分な時間と予算を投下し、得られたデータをもとに最適な工法と安全率を設定します。
無駄のない設計が完成したら、発注方式を見直し、複数の関係者が連携しやすいスキームを整えましょう。
工事が始まった後も、工程管理を可視化してマイルストーンを明確にし、現場の状況をリアルタイムで把握する体制を構築します。
機材や人員の手配に遅れが生じないよう、段取りを徹底して行い、万が一の天候不良や地盤異変に備えた代替計画も準備しておくことが大切です。
これらの取り組みを通じて、施工中の追加費用や再工事によるロスを最小限に抑えるだけでなく、建物の耐久性や安全性も確保できます。
地盤改良とコスト削減は、相反するものではありません。綿密な調査と計画、適切な工法選定、発注方式の工夫、そして現場管理の強化により十分両立できるのです。
設計・コンサル・発注者をはじめとした関係者すべてが情報を共有し、同じゴールに向かって取り組むことで、現場のトラブルを減らし、着実なコスト削減を実現できるでしょう。